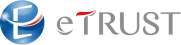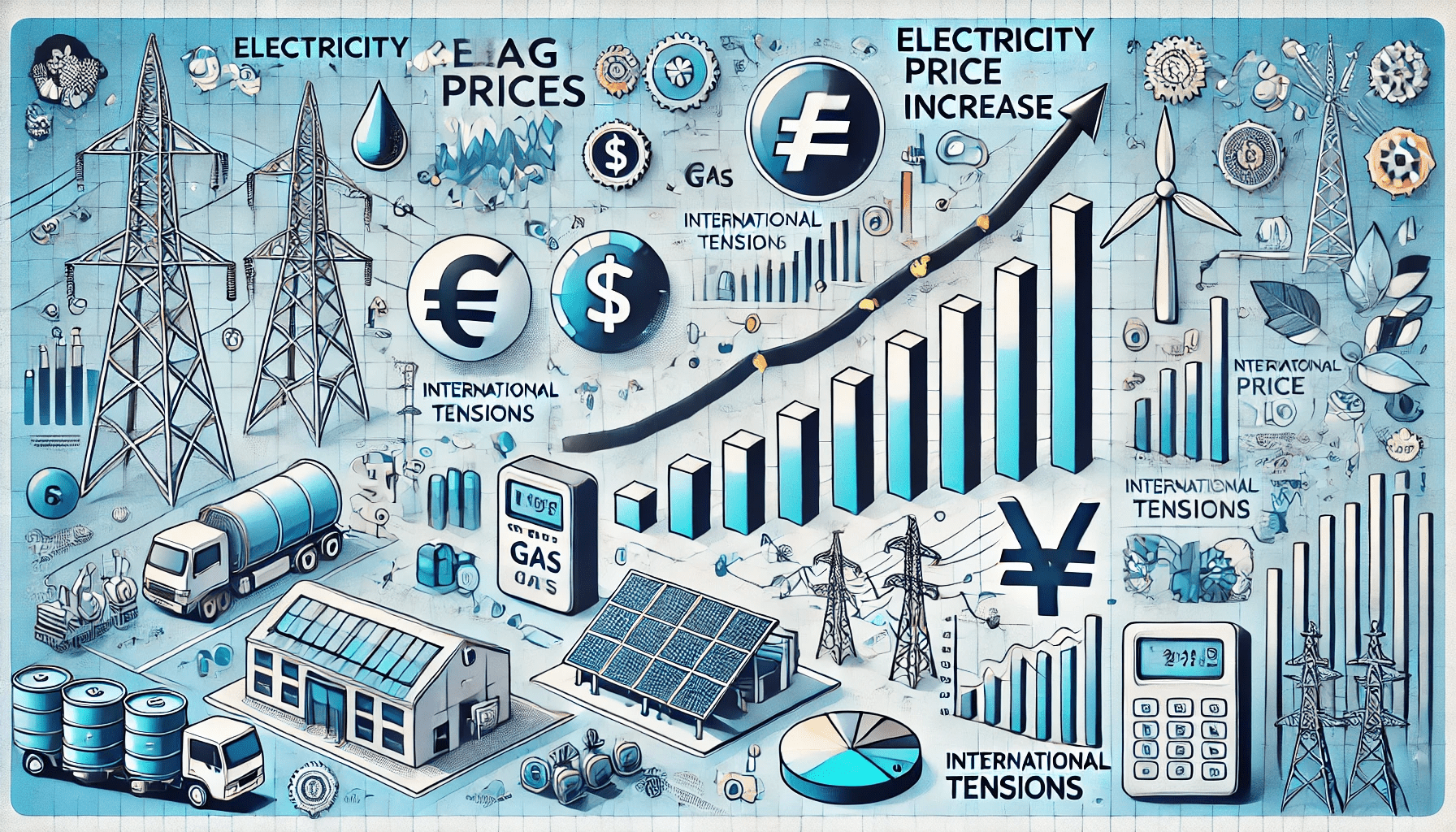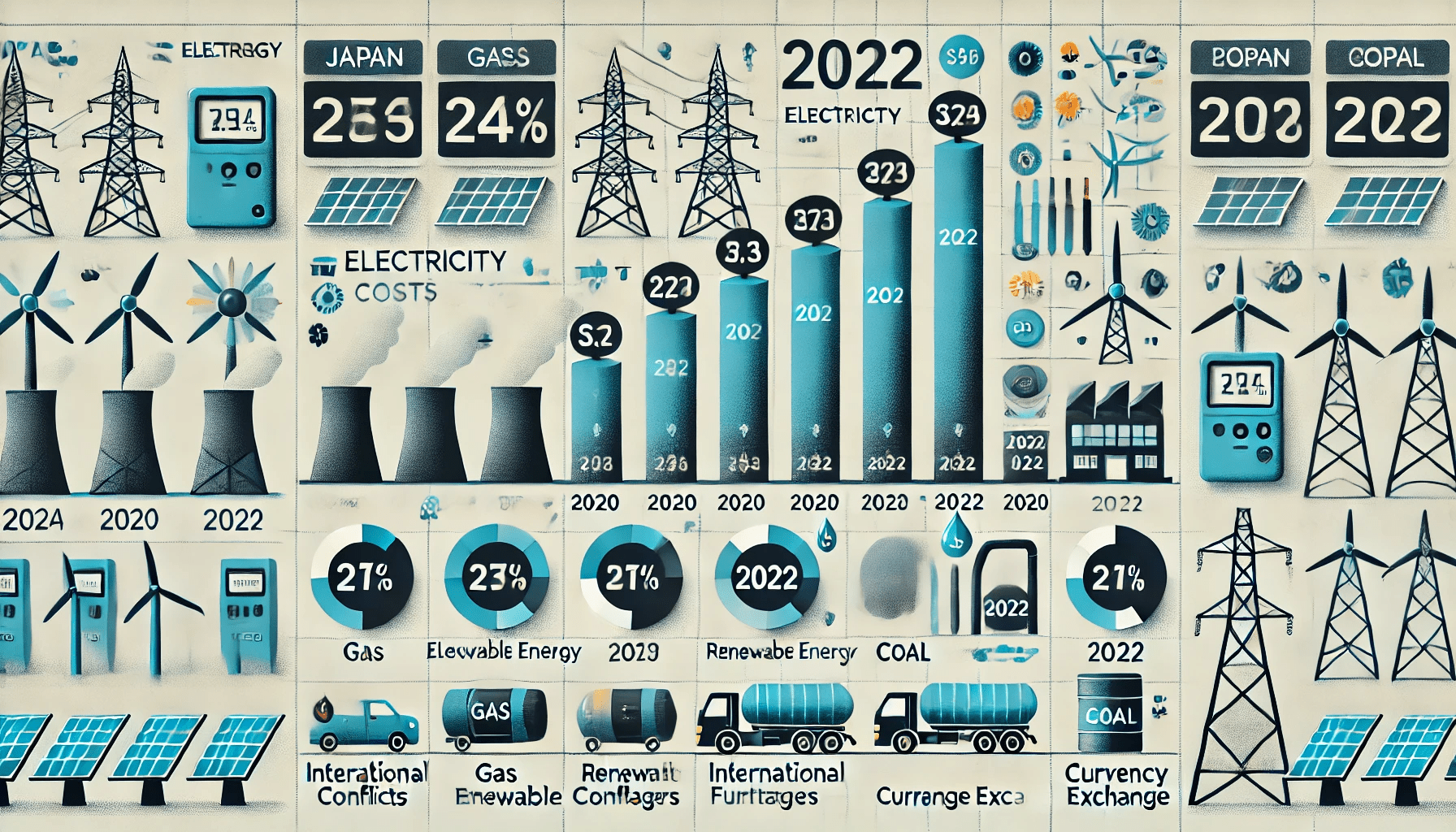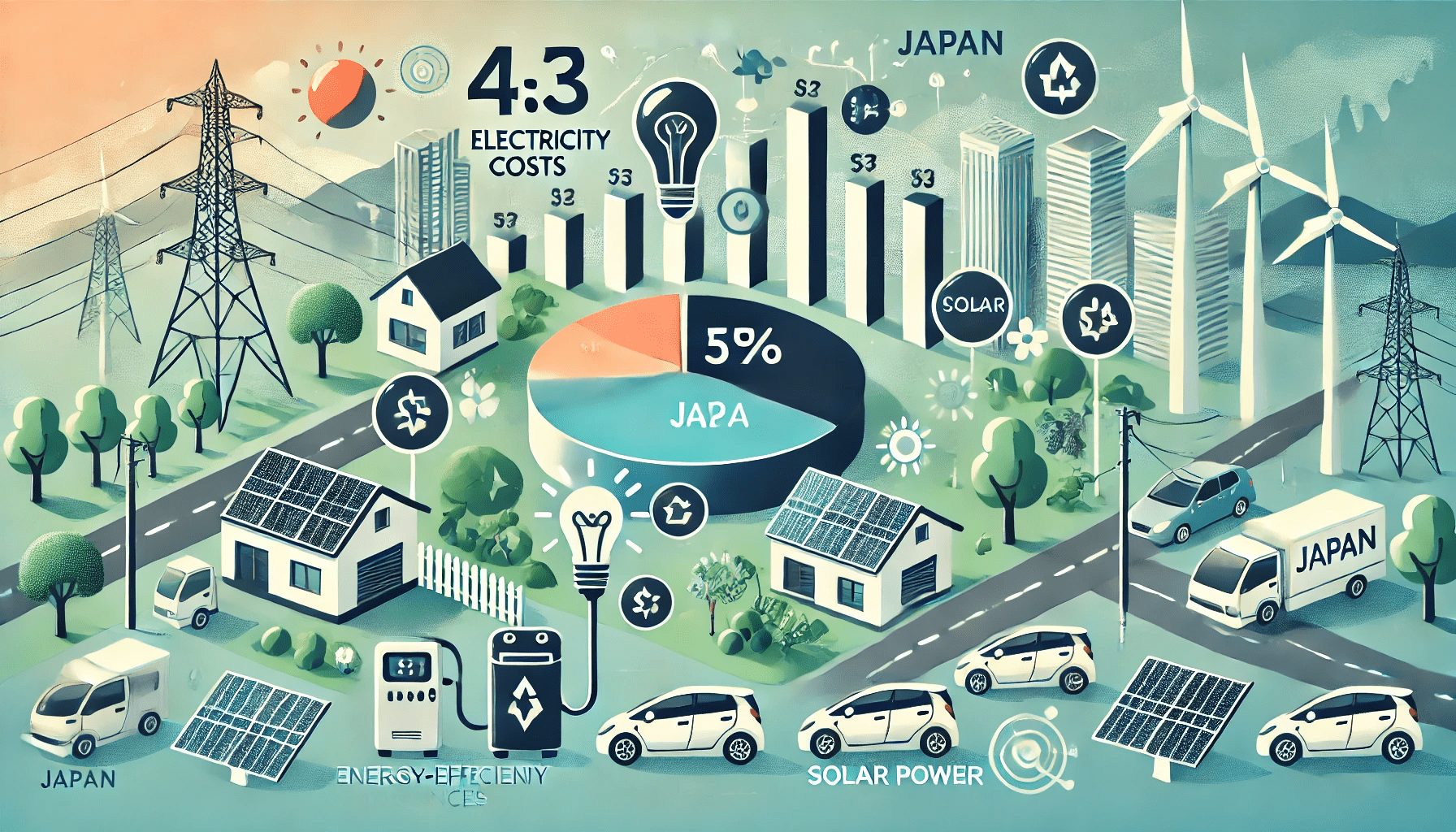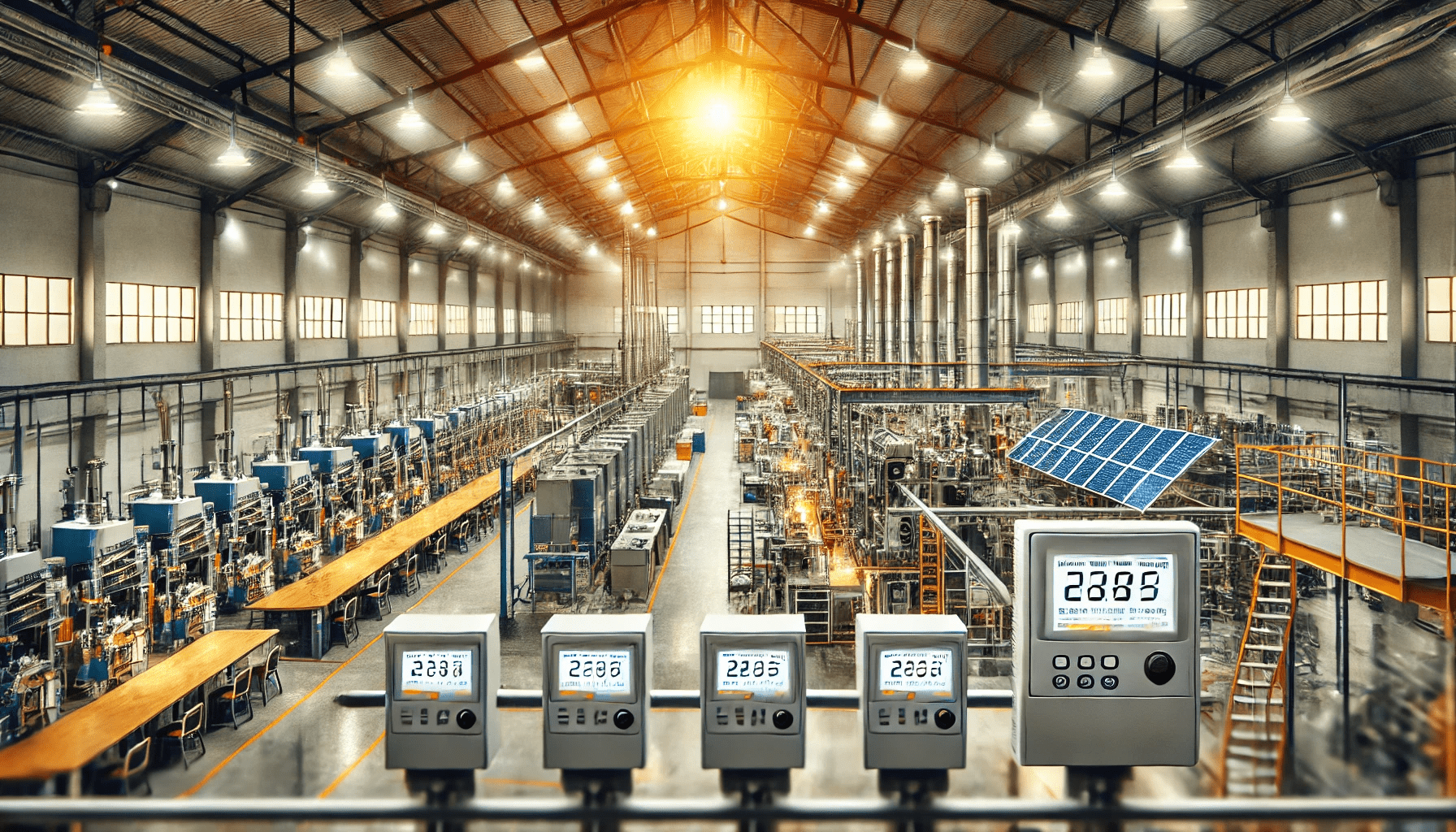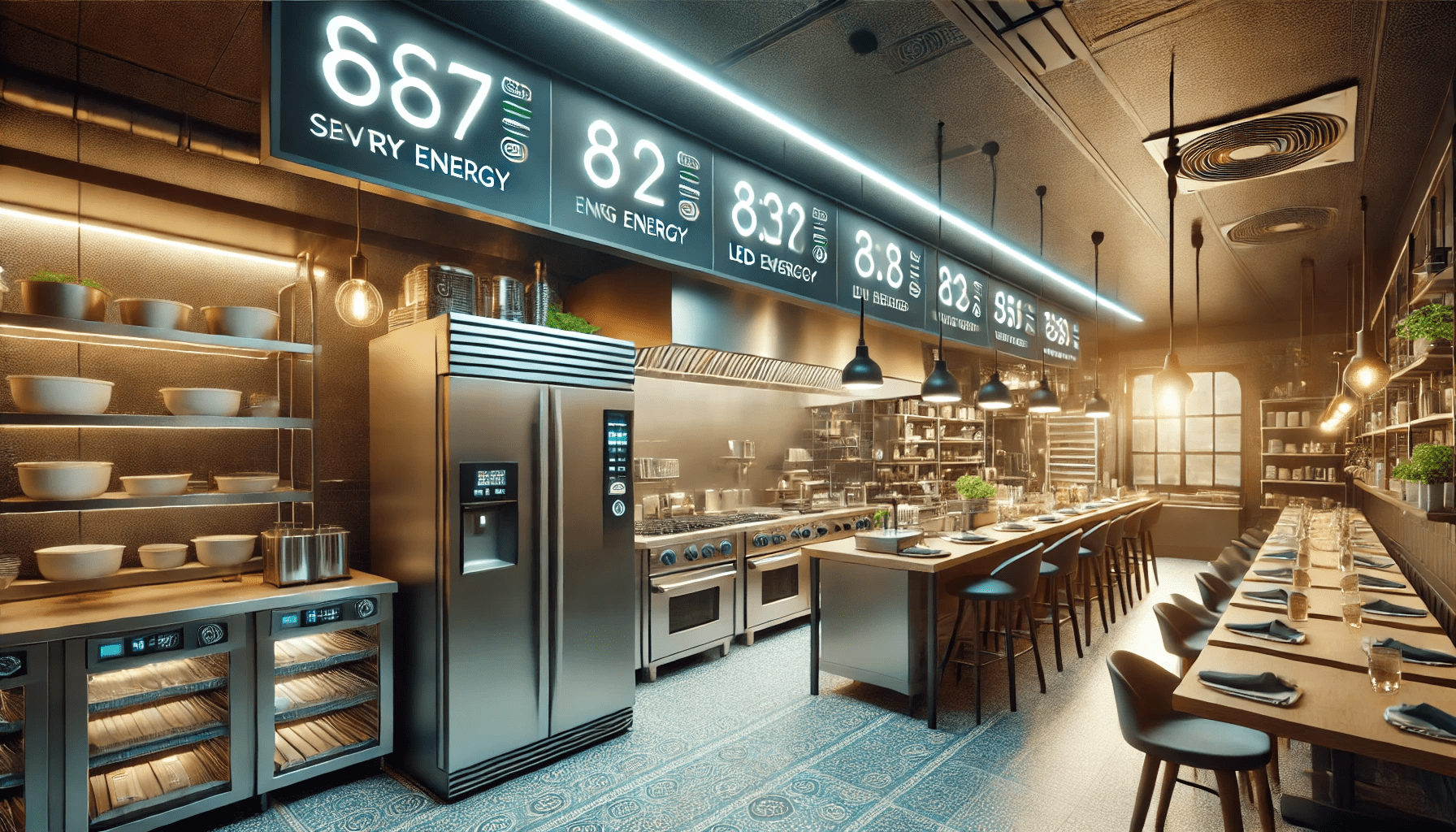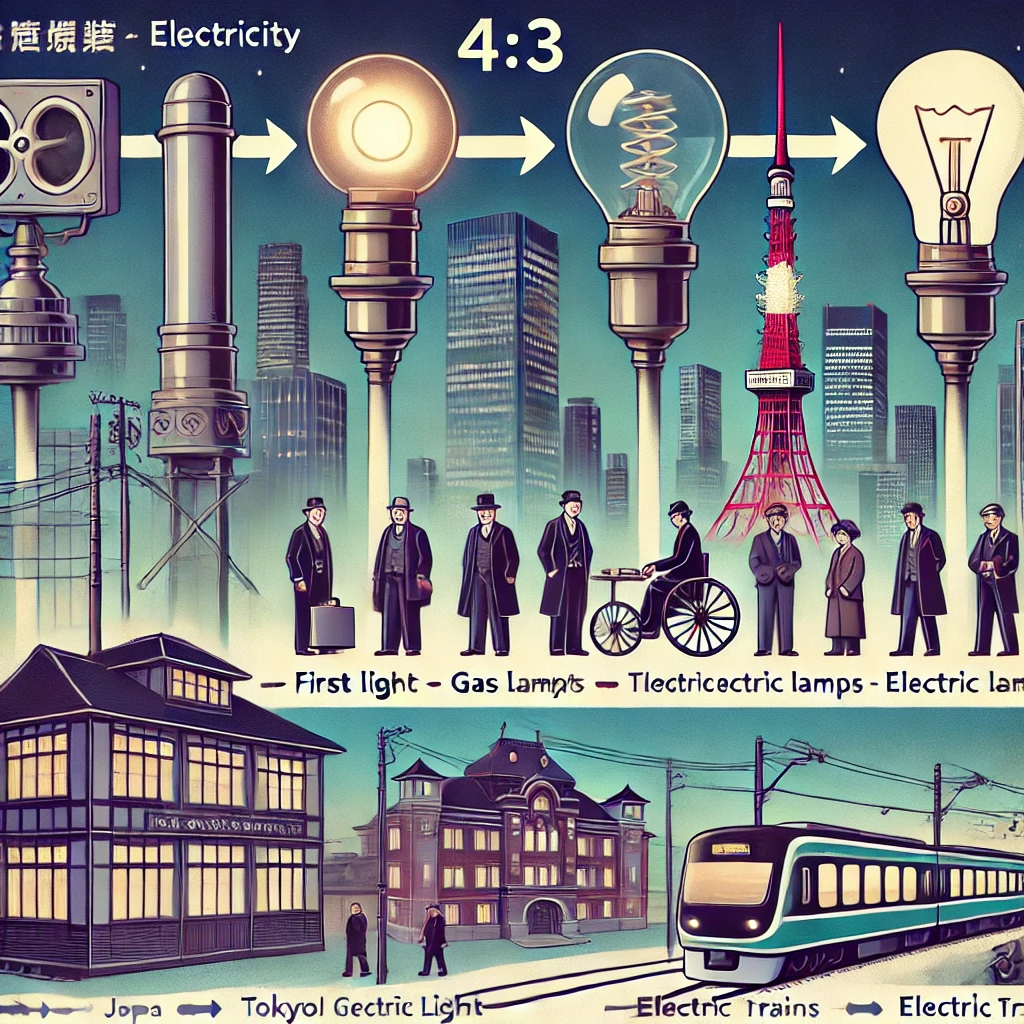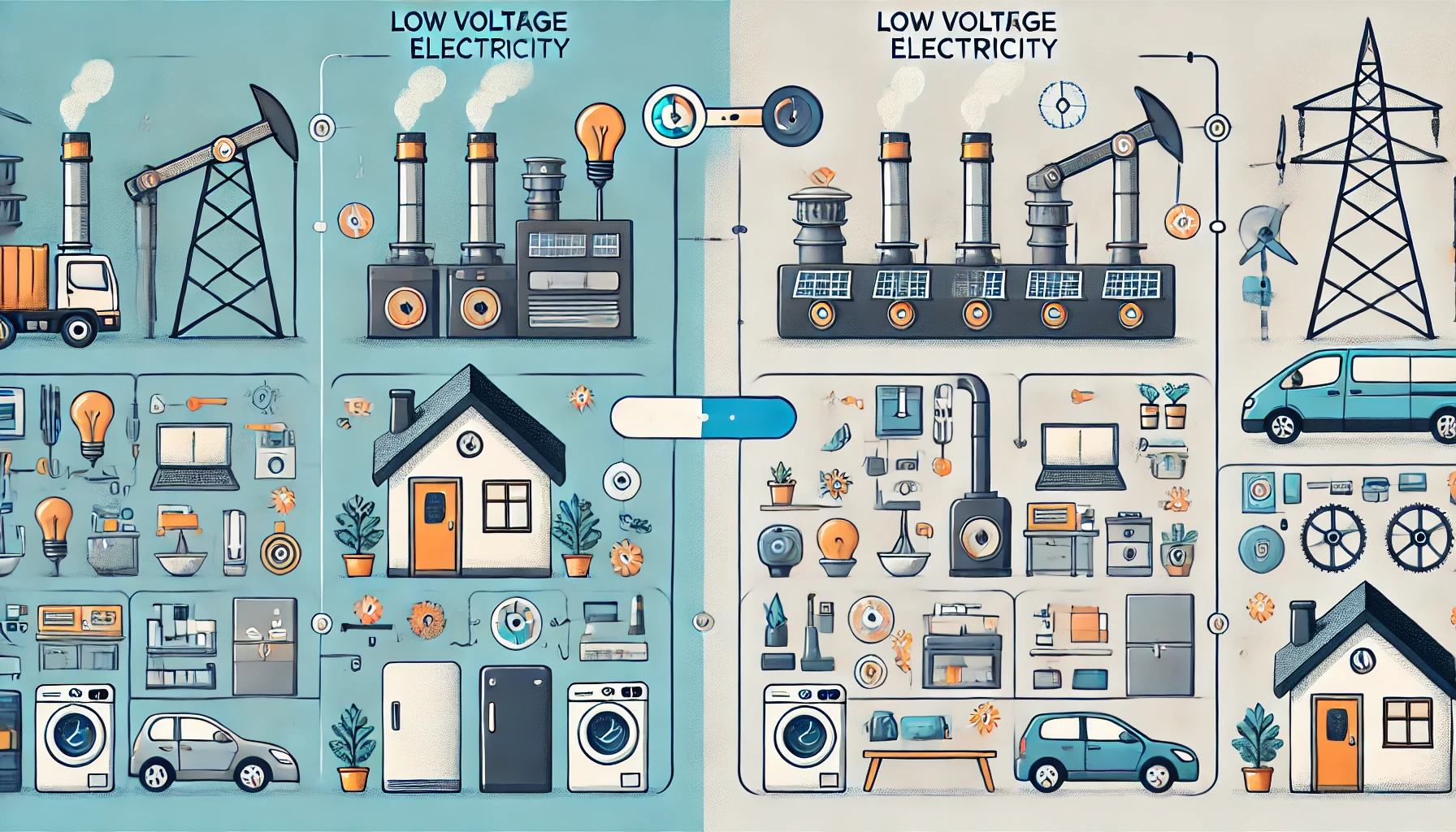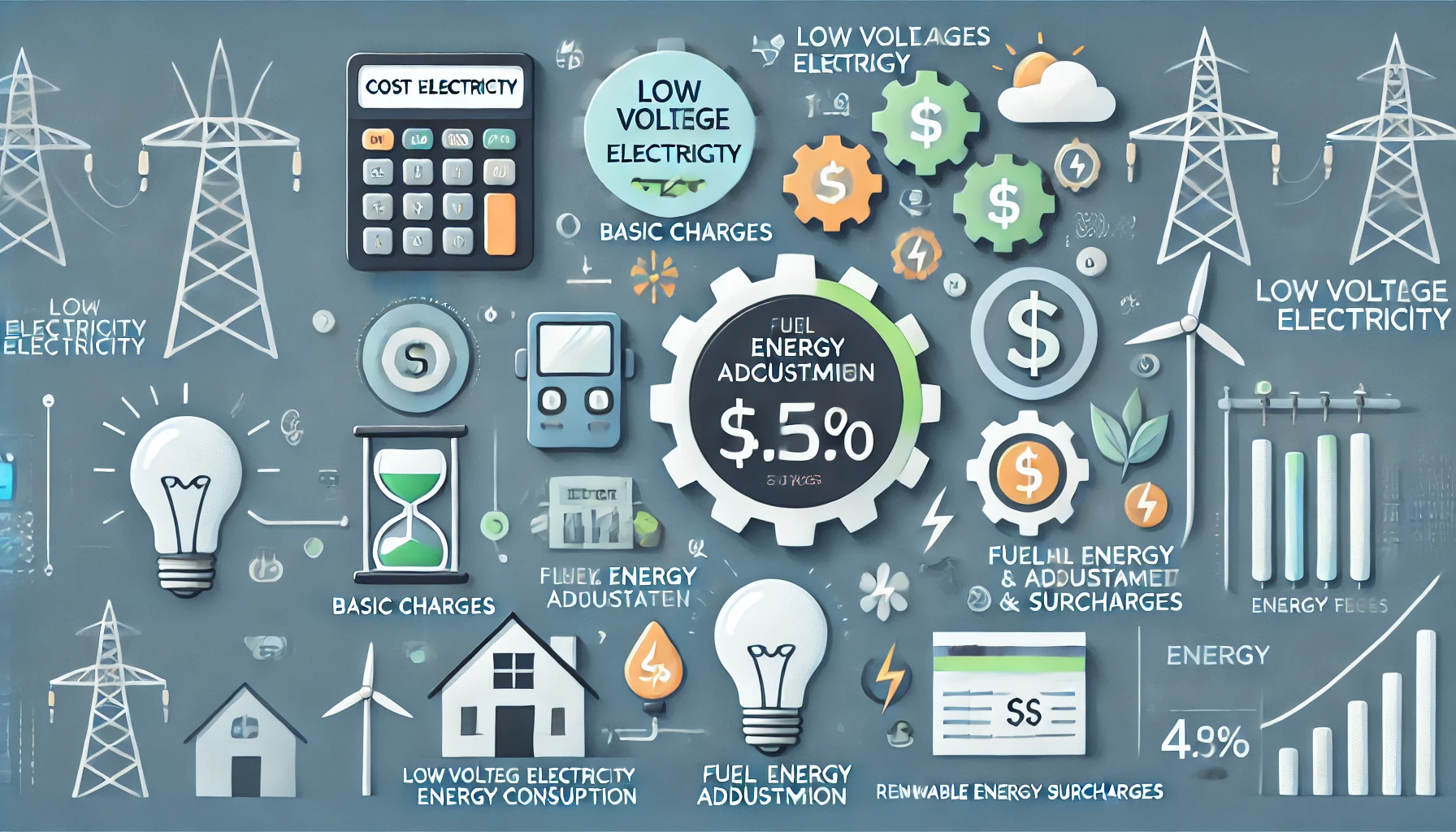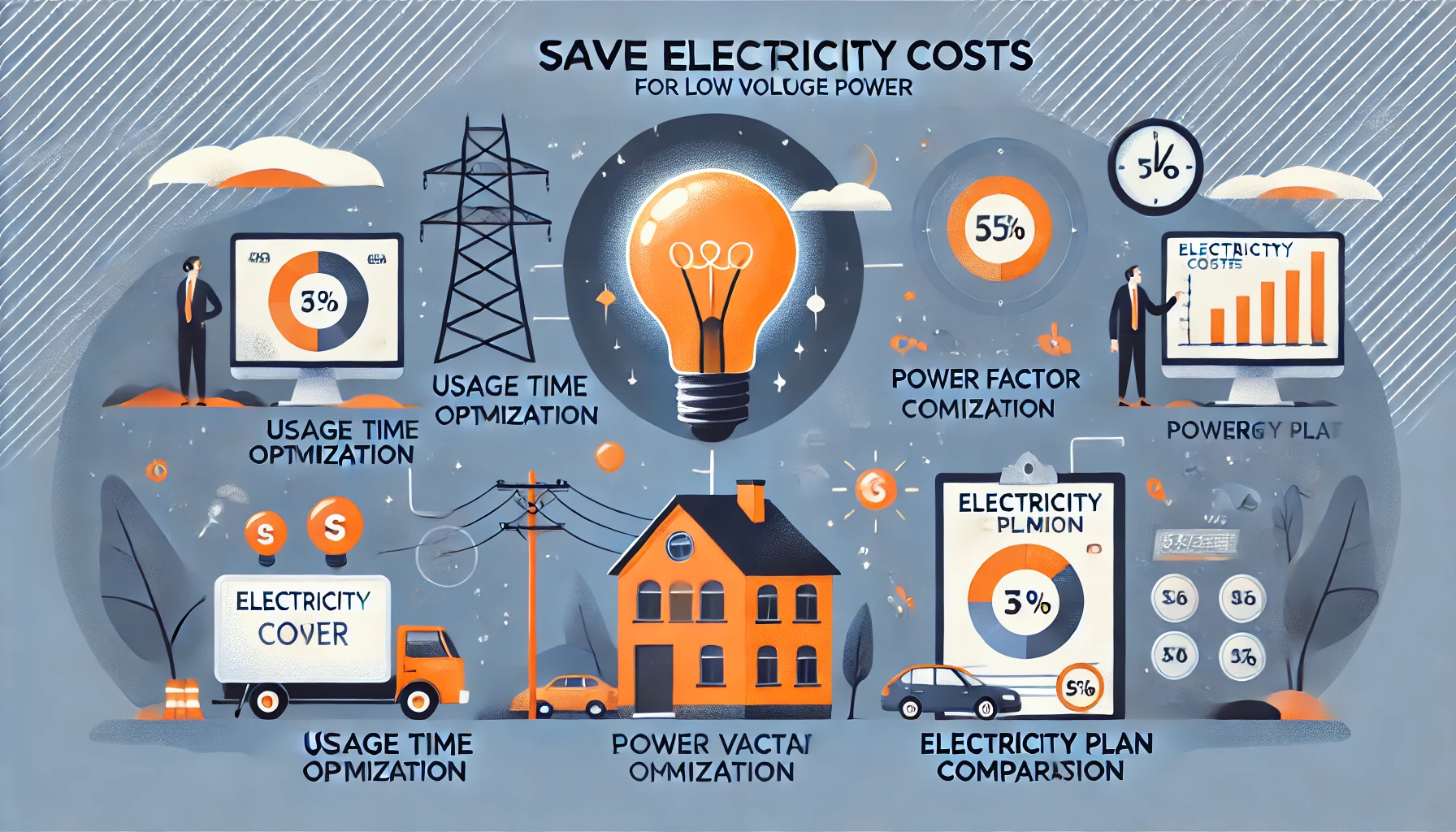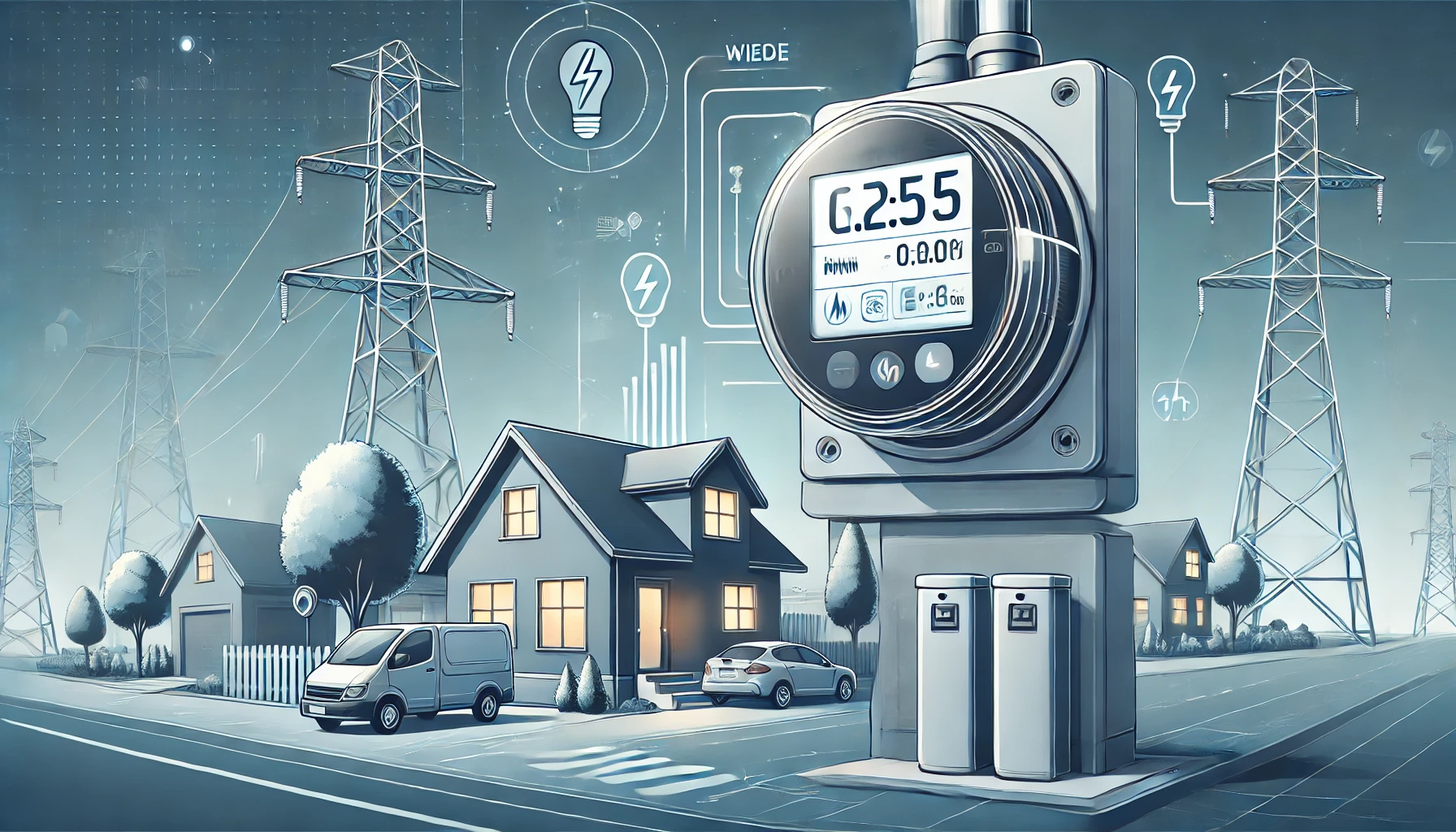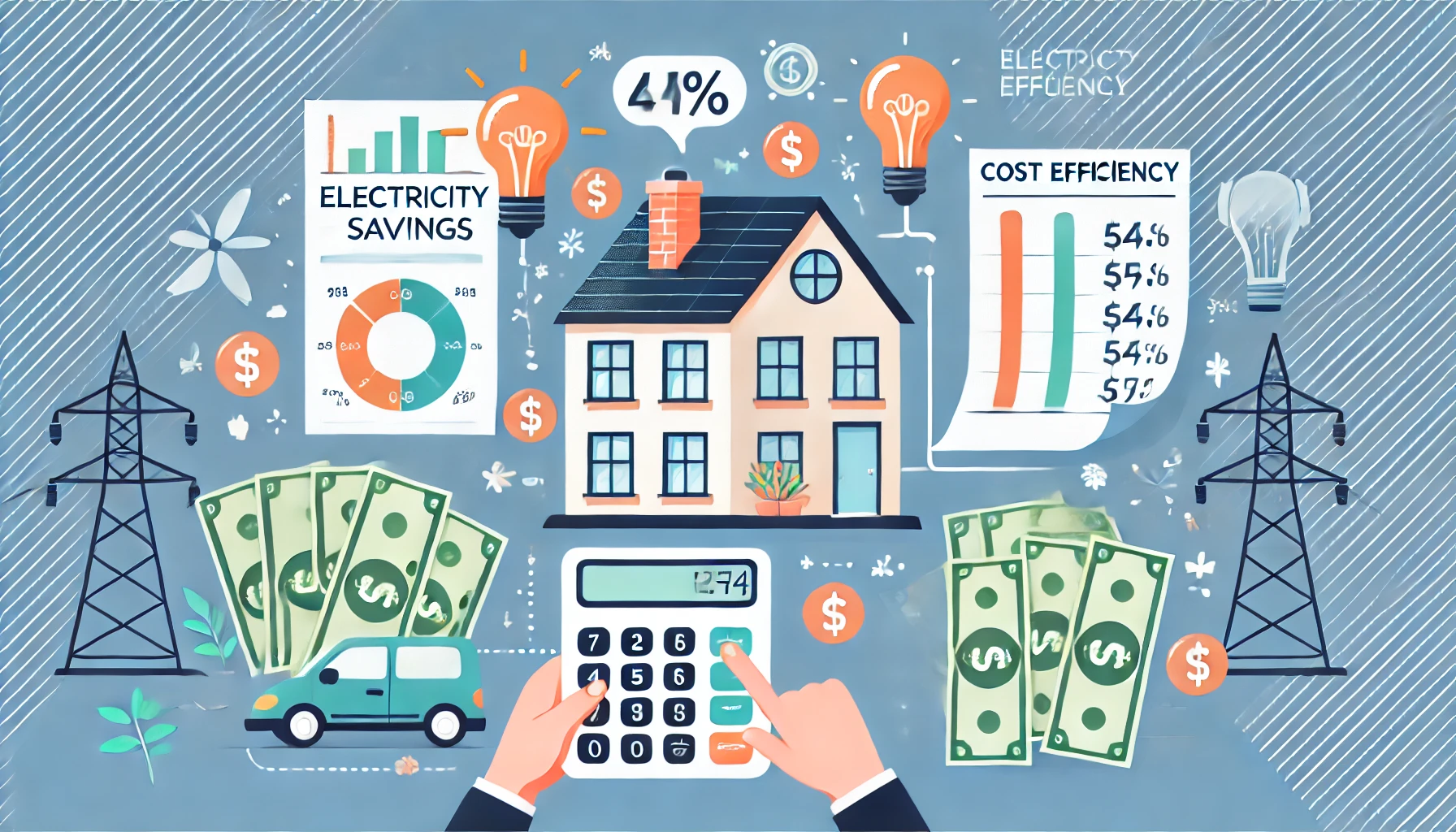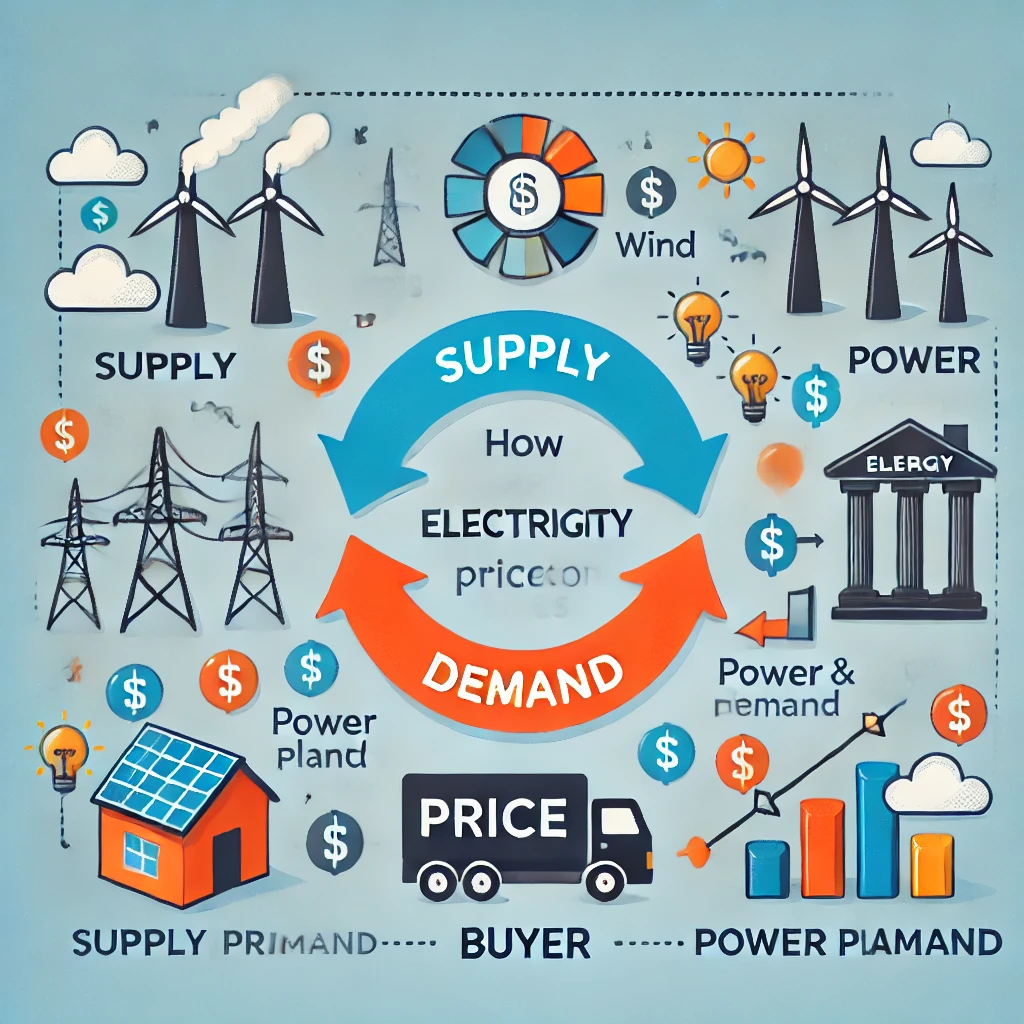電力会社変更の手続き前に知っておくべき必要なもの5選
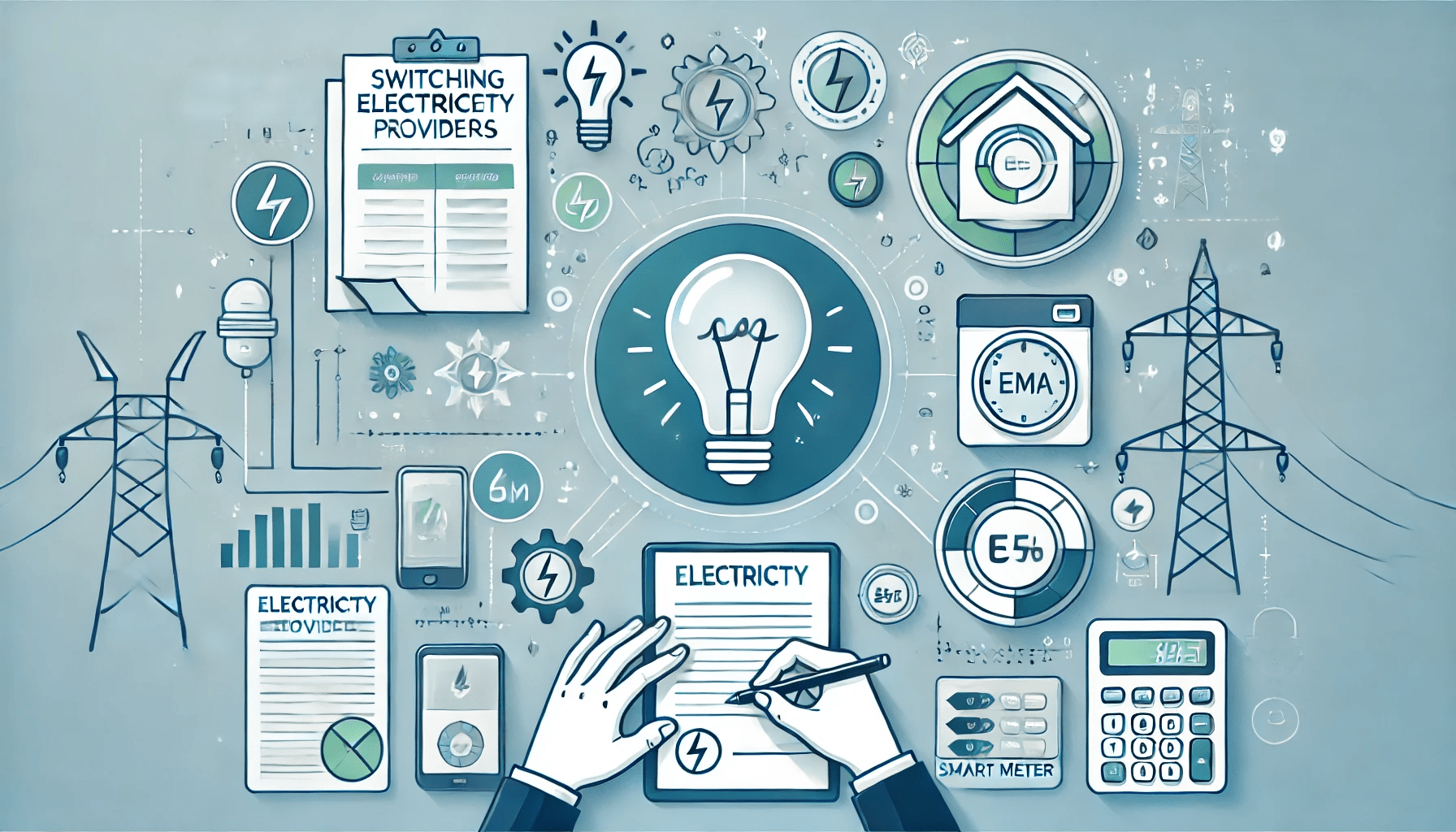
- 1. 供給地点特定番号
- 2. 現在の契約情報 -お客様番号-契約番号-
- 3. 過去の電気使用量・料金明細
- 4. 支払い方法の情報
- 5. 切り替え希望日と手続きの流れ
- まとめ
しかし、電力会社を変更する際には、いくつかの手続きと必要な情報の準備が不可欠です。
「電気代をもっと抑えたい」
「環境に優しい電力を使いたい」
と思ったことがあるなら、電力会社の変更は有力な選択肢です。
ただし、手続きをスムーズに進めるには、事前の準備が大切です。
変更手続きを始める前に必要な情報をきちんと揃えておけば、手続きが簡単に進み、余計なトラブルも避けられます。
この記事では、電力会社変更の際に確認しておくべき必要なものを5つに絞ってご紹介します。
それらをしっかり準備して、安心して電力会社の切り替えを進めましょう。それでは、具体的に見ていきましょう!
1. 供給地点特定番号
供給地点特定番号とは?
供給地点特定番号は、全国共通で電力の供給先を一意に特定するための22桁の番号です。
この番号は、電力会社を変更する際に必要不可欠で、どの供給先にも固有に割り当てられています。
確認方法
供給地点特定番号は、電気料金の請求書や領収書に記載されています。
また、多くの電力会社では、契約者専用のWebサービスからも確認が可能です。
もし確認できない場合は、現在の電力会社のカスタマーサポートに問い合わせてください。
→電力会社ごとの供給地点特定番号の確認方法
なぜ必要なのか?
電力会社を変更する際、この供給地点特定番号がなければ、正確に電力の供給先を特定できません。
新しい電力会社が電気を供給するために、確実にこの番号が必要です。
これがないと、手続きが遅れる場合もありますので、事前に確認しておきましょう。

2. 現在の契約情報 -お客様番号-契約番号-
契約者名とお客様番号とは?
契約者名とお客様番号は、現在の電力会社で使用している契約者を特定するための重要な情報です。
契約者名はそのままの名前であり、お客様番号は契約ごとに付与される固有の番号です。
確認方法
請求書や契約書に記載されています。
最近では、電力会社のマイページやWebサービスで簡単に確認することができます。
もし手元に書類がない場合でも、Webサービスにアクセスすれば、必要な情報が手に入ります。
→電力会社ごとのお客様番号(契約番号)の確認方法
なぜ必要なのか?
契約情報は、新しい電力会社への切り替えをスムーズに行うために必要です。
特にお客様番号は、契約変更時の照合に使われるため、必ず正確に確認しておくことが重要です。
3. 過去の電気使用量・料金明細
なぜ電気使用量が重要か?
過去の電気使用量を把握しておくと、変更後の電力プラン選びがスムーズになります。
どれくらいの電気を使用しているかを確認することで、最適な料金プランを選ぶことができるためです。
確認方法
請求書や領収書で確認可能です。
また、各電力会社のWebサービスにログインすれば、過去の使用量や料金明細を簡単に確認できます。
複数月分を確認して、自分の電力使用パターンを把握しておくと便利です。
プランの選定に役立つ情報
電気使用量に応じて、新しいプランをシミュレーションすることが可能です。
電力会社変更後の料金の見通しを立てるためにも、この情報は欠かせません。
過去のデータを参考に、最適なプランを選びましょう。
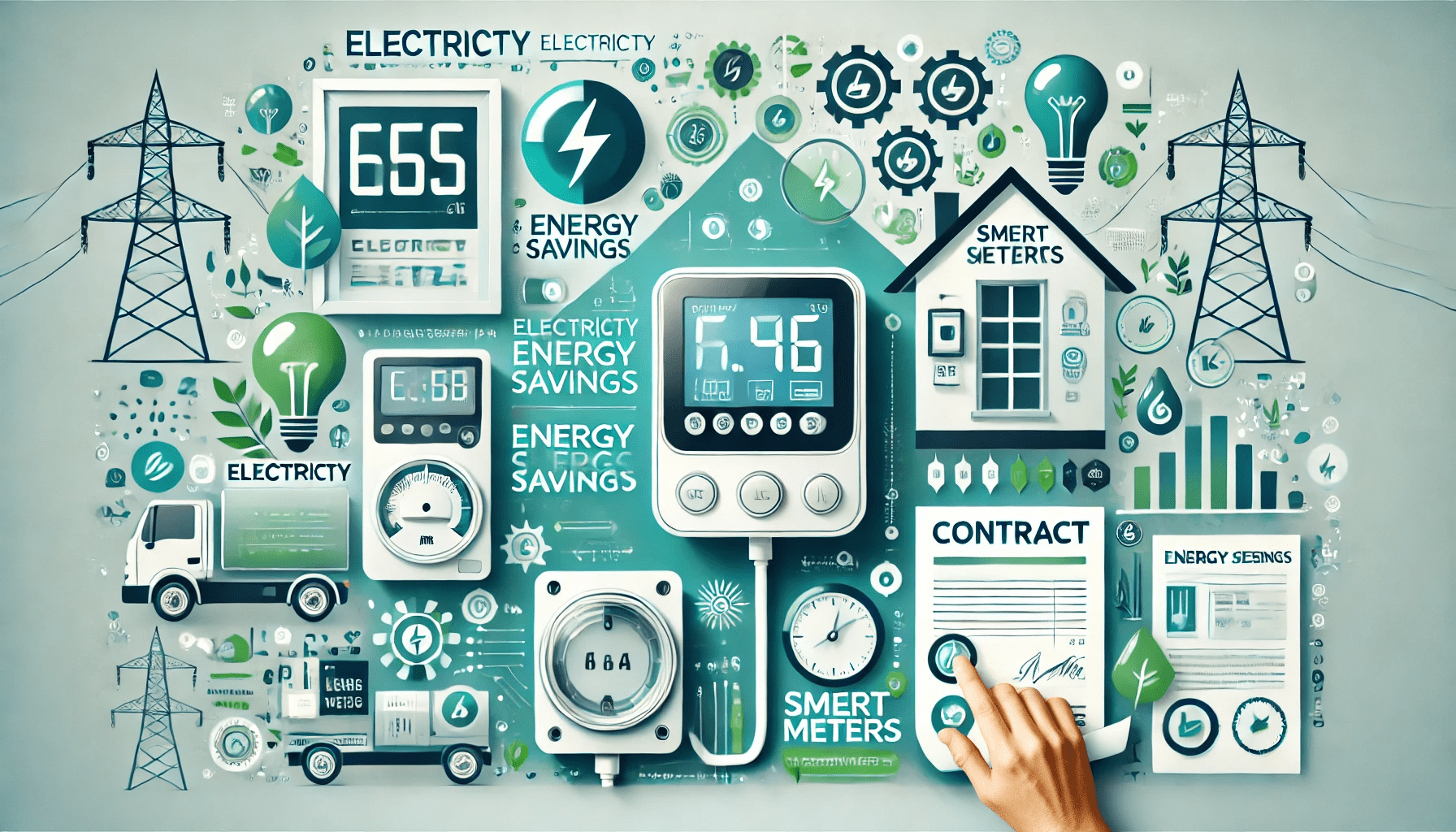
4. 支払い方法の情報
どの支払い方法を選ぶか?
電力会社を変更する際には、支払い方法の選定も重要です。
クレジットカード払い、銀行口座振替、現金振込など、支払い方法によって割引が適用される場合もあるため、事前に検討しておくとよいでしょう。
支払い方法の確認方法
現在の支払い方法を確認するためには、請求書や領収書、またはWebサービスの支払い情報欄をチェックします。
変更後の支払い方法に応じたクレジットカード情報や銀行口座情報を準備しておくことが大切です。
セット割引のメリット
通信サービスやガスとのセット割引を提供している電力会社もあります。これを活用すれば、電気代の他にも通信費やガス代が節約できる可能性がありますので、支払い方法と合わせて検討しましょう。
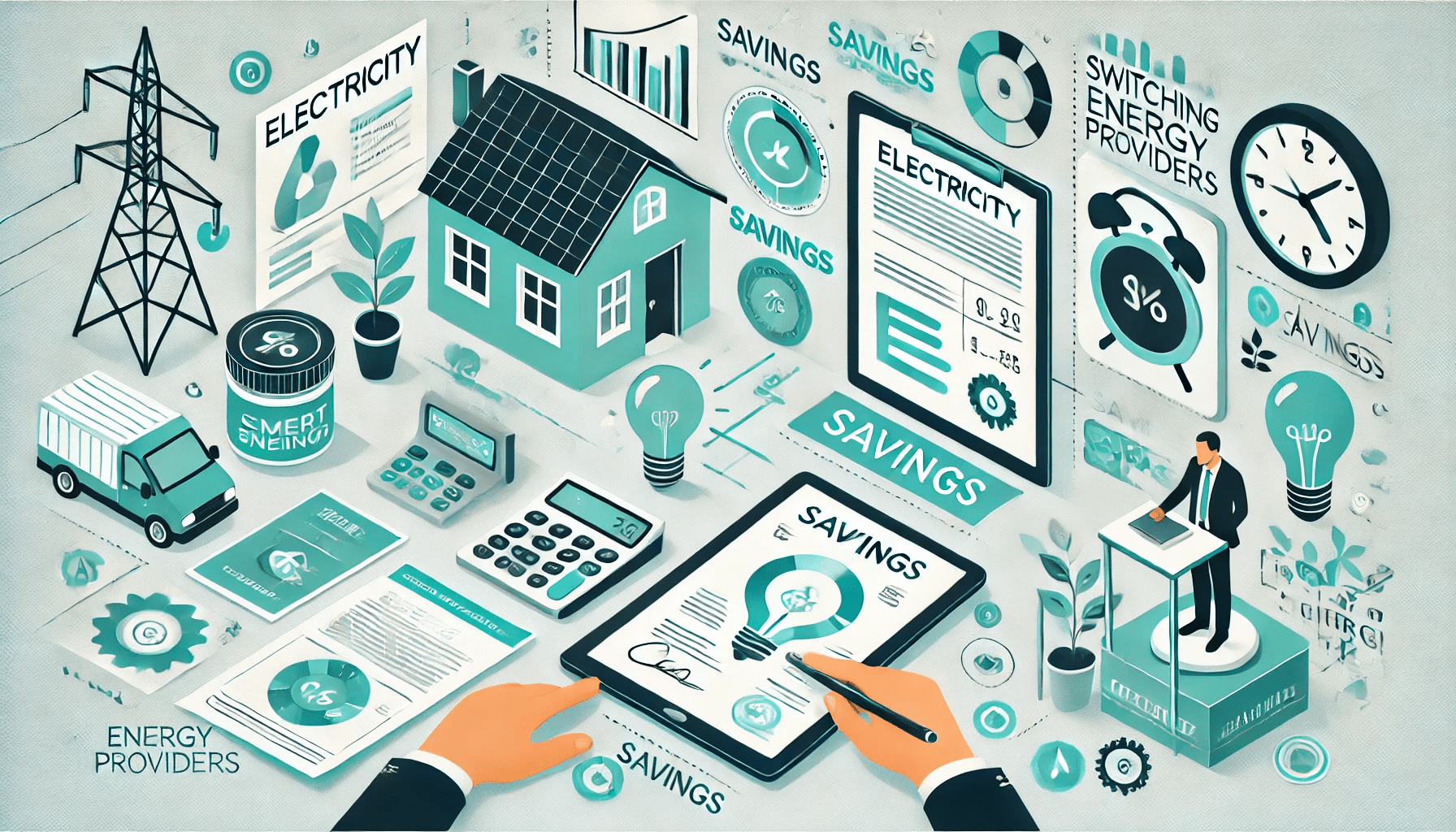
5. 切り替え希望日と手続きの流れ
切り替え希望日を設定しよう
電力会社を変更する際には、切り替え希望日を設定します。
大抵の場合、月末や電力使用量が多い季節を避けると、変更がスムーズです。
手続きの流れを理解する
電力会社の変更手続きは、基本的に新しい電力会社に申し込むだけで完了します。
新しい電力会社が、現在の契約を自動で解約し、新契約を手続きしてくれるため、特に複雑な作業は不要です。
スムーズな切り替えのために
切り替えは基本的に自動で行われ、停電することはありません。
ただし、スマートメーターが設置されていない場合は、新しく設置される必要があります。
これも新電力会社が手配してくれるので安心です。
まとめ
供給地点特定番号や契約者情報、過去の電気使用量、支払い方法、切り替え希望日などを把握しておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。
これらの5つのポイントを押さえて、安心して電力会社の変更を行い、電気代の節約やサービスの向上を実現しましょう。